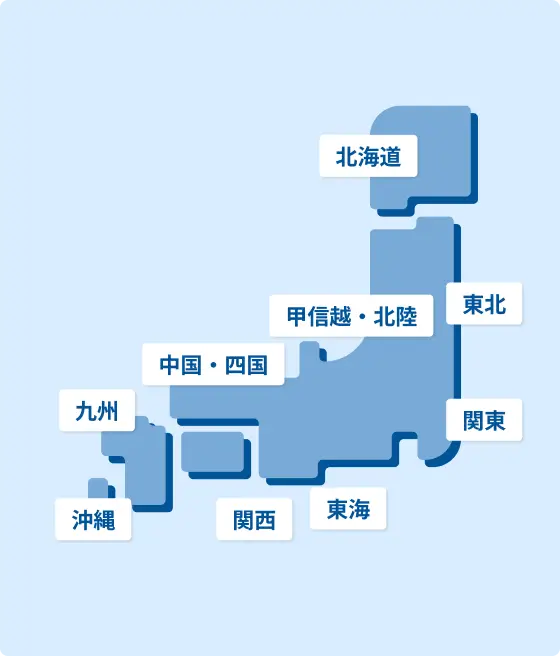目 次


朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す
交通事故トラブルに強い
弁護士を探す
1. 進む交通事故対応のDX化
損害保険会社最大手の東京海上日動火災保険が、2017年4月にドライブレコーダー付き自動車保険を導入して8年が経ちました。交通事故の分野でも他分野と同様に、業務の効率化などを目的としたDX化が進みつつあります。
たとえば、AI(人工知能)がドライブレコーダー映像を解析し、交通事故の過失割合を判定するシステムやサービスを損害保険会社が導入し始めています。これにより、事故処理の迅速化や公正な損害賠償の実現が期待されており、AI技術を活用した交通事故対応の効率化に向けた取り組みが加速しています。
また、交通事故分野を扱う法律事務所においても、デジタルツールやシステムを活用することにより、業務の効率化などを図る動きが進みつつあります。近年では裁判のIT化も本格的に始まっており、オンラインでの訴訟対応が求められる中で、弁護士業界でもDXへの対応が不可欠となっています。
2. 専門家として感じる10年間の変化
筆者は弁護士として業務を始めた比較的初期の段階から現在に至るまで、10年以上にわたり交通事故に関する業務に携わってきました。交通事故を取り扱う弁護士として特に大きな変化を感じているのは、主に以下の2点です。
2-1. ドライブレコーダーの普及
ドライブレコーダーの普及により、事故現場の客観的記録(証拠)が存在する事故が増えてきました。筆者が交通事故に関する業務を始めた10年以上前の時点でもドライブレコーダー自体は存在していましたが、搭載されているのはタクシーやバスなどの事業用車両がほとんどで、普通乗用自動車など家庭用の車両にはあまり普及していないという印象でした。
そのため当時、交通事故相談や依頼を受けた際にドライブレコーダー映像が証拠として提出されるケースは非常に少なく、仮に搭載されていたとしても録画がうまくできていなかったり、上書き保存でデータが消失していたりすることも多々ありました。
「ドライブレコーダーの映像があるかないかでそんなに変わるの?」と思われる方もいるかもしれません。実際に事故発生時の映像が残っているケースと残っていないケースでは、裁判による認定で賠償責任の有無の結論が180度変わるということもあり得ます。
特に事故の状況に争いがあるケースでは、客観的な映像記録は極めて重要です。ドライブレコーダーが無い時代は、映像記録として周囲の防犯カメラ映像の有無を調査することもありましたし、事故の目撃者を探すところから始めるケースもありました。こうした作業は非常に時間と労力を要することになりますし、そもそも有力な映像記録や証言の入手ができないケースも相当数ありました。
事故状況を客観的に証明できる映像記録や目撃者の証言がないケースでは、間接的な証拠を積み重ねて、事故当時の状況を推察するということも必要でした。たとえば車両のキズの付き方や凹み方、その深さなどから、双方の車両の衝突方向(角度)や衝突時の速度などを分析する専門的な調査や鑑定を行う、といった対応が求められていたのです。
もちろん、ドライブレコーダーにしても万全ではなく、たとえば衝突箇所が映像の死角になっていれば、直接的な衝突の瞬間などは記録されません。しかし、そのような状況下でも衝突前後に事故車両が映り込んでいたり、衝突の瞬間の衝撃の強さがカメラの揺れなどでわかったりすることで、事故当事者の供述と照らし合わせれば状況を裏付ける重要な証拠となる場合があります。
このように、ドライブレコーダーの普及により、交通事故実務においては事故状況をより正確に認定できるケースが増加しました。それに伴って証拠収集の効率化、すなわち業務全体の効率化が大きく進んだことは、近年における最も大きな変化の一つだと感じています。
2-2. AIの活用などデジタルツールの導入
筆者はこれまで、交通事故分野において被害者側の弁護士としてだけではなく、加害者側(損害保険会社側)の弁護士としても業務に携わってきました。その中で、AIを含むデジタルツールの導入という観点では、弁護士業界よりも損害保険会社の方が進んでいるという印象を持っています。
損害保険各社における生成AIの活用事例として、お客さま対応(問い合わせ対応)の場面における生成AIの導入(AIチャットボットなど)や、保険の不正請求を防止するためのAIスクリーニングシステムの構築などがあります。これにより、顧客対応や保険金請求に関する業務の効率化が図られています。
また、交通事故の処理対応の場面では、ドライブレコーダー映像などをもとに交通事故の過失割合を自動で判定するシステムや、事故状況を立体的に可視化するシステムを導入する損害保険会社も出てきています。
一方、法律事務所におけるAIやデジタルツールの活用については、損害保険会社と比較するとまだあまり進んでいない印象を受けます。
もっとも、業務の効率化のために、過去の裁判例や、書籍・文献などをオンライン上で検索できるシステムを導入する事務所はかなり増えてきていると思います。また、弁護士が依頼を受けた事件に関して各種の情報・記録を一括管理できるシステムを導入する事務所も一般的になってきています。こうした流れを見る限り、徐々にデジタルツールを利用して業務の効率化を図る動きが広まりつつあるのは事実です。
また、近年、裁判のIT化が進行しており、交通事故を含めた裁判がオンライン(ウェブ上)で完結するようになる制度が今まさに導入されつつあります。弁護士業界においても、今後はこれらの制度に対応すべく各種記録をデータ化し、オンラインで裁判所に書類を提出したり、クラウド上で記録を保管したりする必要に迫られることになります。こうした影響もあり、徐々にかもしれませんが、弁護士業界においても、DX化が進んでいくことになるでしょう。
さらに、直接的なAI導入とは異なりますが、医療機関における電子カルテの普及も、交通事故実務に携わる弁護士にとって大きな変化の一つです。交通事故の業務においては、医療記録の精査・検討が不可欠であり、ときには膨大な量の医療記録を読み込まなければいけないケースもあります。手書きのカルテが主流だったころは、専門用語や医学用語の略語が多い医療記録の判読が困難なことも多く、内容を理解するのに相当な時間を要するケースもありました。
電子カルテの導入により、より読みやすく、構造化された医療情報として記録が提出されるケースが増えています。医療記録の読み込みや分析にかかる時間が短縮され、業務の効率化という面で多分に寄与しています。


朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
3. AIの導入による交通事故実務の改善例
生成AIの導入により、交通事故事案に関して現場の業務の効率化が図られつつあることは先述した通りです。
例えば、あいおいニッセイ同和損害保険はAIによる過失割合の判定サポート機能を導入しており、生成AIがドライブレコーダーの映像から事故状況の可視化や相手車両の速度推定をしたうえで、事故の状況図を自動で作成してくれるサービスを提供しています。どちらの車両にどの程度責任があるのかという「過失割合」を過去の事例からスムーズに判定してくれることもあり、特に物損事故の解決日数が短縮されるなど迅速な事故解決に貢献しているようです。
このように、これまで人間が情報を分析して検討していたものをAIにサポートしてもらうことで業務の効率化が図られ、結果としては加害者、被害者双方にとって解決までの日数を短縮できるというのが、こうした生成AIのシステム導入のメリットといえるでしょう。
弁護士の業務においても、生成AIの利用により交通事故業務でのリサーチにかける時間を大幅に短縮できるようになりました。従来は膨大な文献や判例データベースを一つひとつ検索していた作業が、AIによって大幅に簡略化され、初期分析や検討にかかる時間を減らせるようになってきています。
4. AIの導入によって複雑化していること・AIでは行き届かない課題点や問題点
ただし、弁護士の業務に限ってみると、生成AIの利用には現時点ではいまだ課題が多く、注意が必要だと筆者は考えています。
【裁判例の誤認など、生成AIの精度に対する懸念】
弁護士の重要な業務の一つに、「過去の裁判例」を調べる作業があります。たとえば、交通事故の案件であれば、依頼者のケースが裁判でどのように判断される可能性があるかを予測するために、類似の裁判例を参照しながら今後の進め方を検討していきます。
筆者は実際に、ChatGPTに対して「過去に似たような交通事故での裁判例はあるか」という質問をしてみたところ、筆者が探していたケースと同じようなケースで判断が示された裁判例があるとの回答が返ってきました。そこには、裁判の判決が下された日付や判決を下した裁判所も記載されており、一見すると、本当にその裁判例があるかのような要約がなされていました。ところが、その内容に少し違和感があったので、筆者が、普段使っている裁判例の検索システムでその日付や裁判所での過去の裁判例を調べてみたところ、実際にはそのような裁判例は存在しないことがわかりました。
これは単なる偶然ではなく、試しに色々な形で裁判例に関する質問をしてみましたが、あたかも実際の裁判例があるような回答が出てくるものの、実際にはその基となっている裁判例は存在しない、というようなことが何度か起こりました。これは筆者だけの経験ではなく、ほかの弁護士で同様の経験を語っている方もいます。
ここからわかる注意点としては、特に専門性の高い分野におけるAIの回答に関しては、必ず人の手による正確性のチェックが必要ということです。もちろん、これらはあくまでも「筆者が利用した時点」におけるAIの正確性です。生成AIの性能は日々進化しており、将来的には高い正確性と信頼性を備えたツールへと成長することが期待されています。
【AIでは判断しきれない複雑なケースの存在】
もう一つの課題として、AIはあくまでもAIであり、法的な判断を求められる場面、とくに複雑な事故のケースでは、最終的には人間の判断が必要だと考えられることが挙げられます。
AIが過去の事例などを基に、交通事故の処理の方針を示し解決に導くことについて考えてみます。たとえば、「ケガ人がいない物損事故のケース」や「賠償の内容がある程度類型化している典型的な事故のケース」であれば、双方が納得するような解決案がAIによって示されるということも十分考えられます。
一方で、過失割合の判定も含め、これらのAIによる判断はあくまでも「過去の事例」の引用や比較によって示されます。事故状況やケガの状況が複雑で、被害者への賠償を行う項目が多岐にわたり、あるいは、後遺症の有無やその程度が争われる場合など機微な判断が要求されるケースでは、過去の事例との単純な引用や比較では判断が難しい場合もあります。このようなケースではAIによる判断では不十分となることも考えられます。
こうした複雑で入りくんだケースでは、やはり人間がさまざまな観点から検討し、議論を交わして協議し、それでも合意に至らなければ、最終的には裁判官の判断によって結論が示されるということが必要でしょう。AIではなく、弁護士や裁判官が知恵を振り絞って、可能な限り適切な形での解決を図るということが引き続き求められるのではないかと思います。
【当面は補助的な活用が現実的】
さらに、交通事故案件は、とりわけ被害者・加害者それぞれの立場が存在し、慰謝料や損害賠償の金額をめぐって感情的な側面も関与してきます。こうした点まで含めて解決策を提示するには、単なる過去の事例の機械的な当てはめでは不十分であり、感情面にも思いを巡らせることができる人間としての判断力や洞察力が求められる場面が今後も残るでしょう。
将来的には、より高度なリーガルテックの導入が進み、交通事故の解決にも一定の自動化が導入される可能性はあると考えられます。とはいえ、少なくとも当面の間は、AIの回答や情報提供に関して、その正確性や妥当性に全幅の信頼を置くのではなく、AIはあくまでも業務のサポート役や便利なツールとして利用していくのがよいのではないかと考えています。
5. 交通事故対応業務の未来への考察
今後、車両の自動運転化が進むことで、人為的要因による交通事故が減少していくことが期待されています。その結果として、交通事故分野における弁護士の業務は、将来的にかなり減少するのではないかという見通しも存在します。
これまで交通事故分野の業務に携わり、事故によって悲惨な被害に遭われた方々に接してきた筆者としては、自動運転化が進むことにより事故自体を減らすことができるのであれば、その方向性には大いに賛同できます。
もっとも、自動運転化がある程度実現したとしても、交通事故自体が完全になくなるのはもう少し遠い未来の話であり、また、AIの発展・進化によっても、完全に人の手による判断や解決が不要になることは無いのではないかと考えています。むしろ、自動運転化によって新たなトラブルや法的問題が発生し、その対処が必要になるということも十分に考えられます。
社会や技術がDX化していく中で、弁護士としての役割や果たすべき責任は決してなくなるわけではなく、新たな形への変化を求められることになりそうです。
(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)


朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す